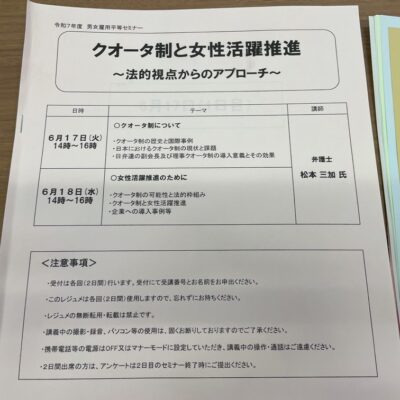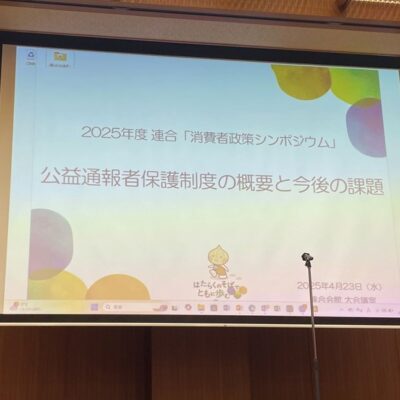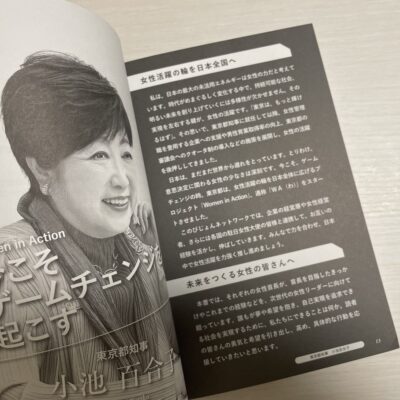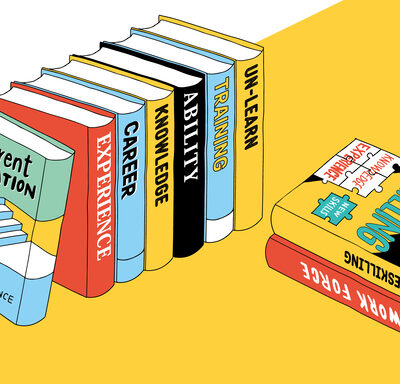こんにちは。古今東西の名作映画を取り上げ、主人公や登場人物をキャリア形成の視点で捉え、人生のヒントを学んでみようというコーナーです。
※ネタバレがありますのでご注意ください。
※映画評やキャリア論を語るものではありません。
桜桃の味
今回は1997年イラン映画「桜桃の味」を取り上げたいと思います。監督・製作・脚本はアッバス・キアロスタミ。第50回カンヌ国際映画祭で今村昌平監督「うなぎ」と共にパルム・ドールを受賞した作品です。
自殺計画
さっそく、主人公バディのキャリアについて見ていきましょう。
現在、彼は自殺を手伝ってくれる人を募集中です。車を走らせながら目星をつけた人物に声をかけ、大金をちらつかせては「簡単な仕事だ」といって強引に仕事を引き受けさせようとしています。
このため、今回は自殺防止の観点から、彼を無条件に受け入れるべくとことん傾聴し、表情やしぐさなどもよく観察して共感的な態度をとりながら映画を観ていきたいと思います。
若者兵士
彼は、クルド地方出身だという兵役中の若者を車に乗せます。嫌がる若者をむりやり現場(墓穴)に連れていき、そこで自殺計画を説明しますが、若者は「面倒に巻き込まれたくない」といって走って逃げ出してしまいました。若者からすれば不気味な話ですので、当然といえば当然でしょう。しかも、彼は理由も告げず「言われたとおりにすればいい、お金は払うから」と一方的です。これでは誰だって、彼を助けようという気になるはずがありません。
神学生
次に、神学を勉強しているというアフガン人の学生をドライブに誘います。彼はこの学生を気に入ったようすで、こう語ります。
『神は人間に命を与え、時がくれば取り上げる。だがその時を待てないこともある。疲れ果てて待てなくなる。だから自分でその時を作る』
ここはすかさず「もう待てないくらい疲れ果てたんですね。よほどつらい思いをしているのですね」といって彼の気持ちに寄り添いたいところですが、彼の話は止まりません。
『人生を捨てようと決意した。その原因は、、話しても君のためにならないし話したくない』
『君にはきっとわからない。わからないが問題じゃなく同じ苦しみは感じない』
『頭で理解したり、同情はできても、心の痛みは感じ取れない。君には君の、僕には僕の苦しみがある。他人の痛みを感じるのは不可能だ』
彼の話を黙って聴いていた学生は、いよいよ神を持ち出して「自分を殺してはだめだ」と説教を始めます。しかし、彼はまったく聞く耳を持たず、それどころか自殺についての持論を展開し、学生を論破しようとします。学生はそれでも彼を食事に誘うなどして自殺を思いとどまらせようとしますが、最後までその想いは伝わりませんでした。
老人
学生と別れた後、こんどはある老人を車に乗せます。
『どんな悩みにも解決法はある。だが黙っていられては誰も助けてやれない』
老人はそう言って、悩みを語ろうとしない彼に困惑しながらも、子供の白血病の治療代のために仕事を引き受けるのでした。
黙って俺の言うことを聞けと言わんばかりの彼。しかし、ここはさすがの年の功。老人が一枚上手でした。老人は彼の知らない道を(自分は知っているといって)走るよう指示し、自分のペースに持ち込みます。そして、自分も若いころ自殺しようとしたと打ち明けるのでした。
桑の実に命を助けられたと言って、ものの見方の大切さを説き始めます。ユーモアを交え、人生を汽車になぞらえ、大自然の美しさや慈しみを語り続けます。さらに、老人は詩を読み、自分たちは友達だといい、約束は必ず守るといって安心させ、手付金は受け取らず、きっと再会できると言い残して車を降りました。
そんな老人の想いが伝わったのか、彼の心は少しずつ変容していきます。そのようすはテヘランの黄昏とともに美しく描かれています。
生と死の間で
ところで、見ず知らずの他人から「自殺するから手伝ってくれ」と誘われたらどうしますか?
自殺予防について考えたとき、厚生労働省「WHOによる自殺予防の手引き」において、その内容や対処方法が詳しくまとめられていましたので少しご紹介します。
この手引きによれば、『自殺について語る患者は滅多に自殺しない』というのは誤解だとしています。また、『患者がすでに自殺の計画を立てていて、その方法まで手に入れているかどうかを知ることは重要である』とも述べています。
誤解 『自殺について語る患者は滅多に自殺しない。』
事実 『自殺する患者は普通前もって何らかのサインを発している。自殺をするとほのめかすような場合は真剣に受け止めるべきである。』
出典:厚生労働省「WHOによる自殺予防の手引き」 (PDF p.6)
患者がすでに自殺の計画を立てていて、その方法まで手に入れているかどうかを知ることは重要である。銃で自殺するつもりだといっても、銃を手に入れる方法がなければ、自殺の危険は比較的低い。しかし、計画をすでに立てていて、具体的な方法(たとえば、薬)を手に入れている場合、あるいはその方法がすぐに手に入るような場合は、自殺の危険は高い。
出典:厚生労働省「WHOによる自殺予防の手引き」 (PDF p.6)
この点、彼は自殺について語っていることは明らかであり、自殺について具体的な計画を持っていることも分かりました。
注目すべきは計画の中身です。彼は自殺を一人で完結させようとはせず、他人を巻き込む形で成立させようとしています。これはひるがえって、自分が自殺を考えているということに気づいてほしかったのではないでしょうか。すなわち、彼は「死にたい」と「生きたい」という相反する感情がせめぎ合っている状態(両価性)にあったと考えられます。
また、先の若者兵士とのやり取りでも、彼の心情が見え隠れする様子が描かれています。それは、若いころ彼にも軍隊経験があって、その時の思い出を話しつつ「僕は仲間じゃないか?」と若者に投げかけるシーンです。彼は仲間意識を持つことで、人とつながりたかった(=孤独から抜け出したかった)のではないでしょうか。
人生観
試しに、彼の存在を「死」の象徴として捉えたらどうなるでしょうか。若者兵士は死と出会って逃げ出しました。神学生は死と出会って神を語りました。そして、老人は死と出会って人生の美しさを謳いました。死と出会うことで三者三様の人生観があぶり出されたような、そんな気がします。
もし、自分の人生観をあぶり出したいなら、死について考えてみるのもよいかもしれませんね。
それでは、またいつかどこかでお会いしましょう。