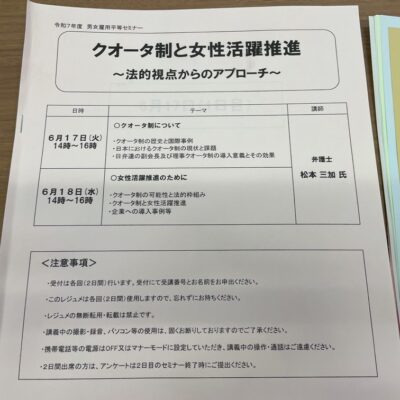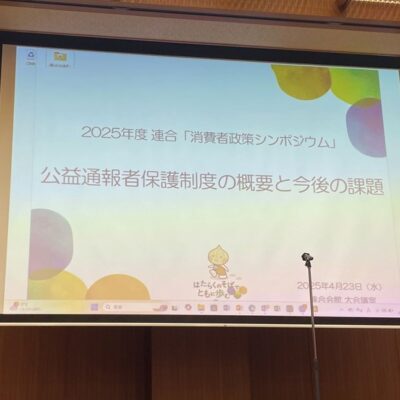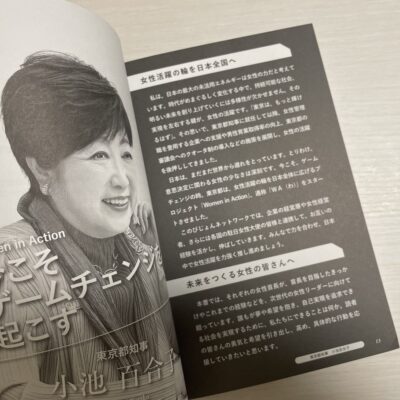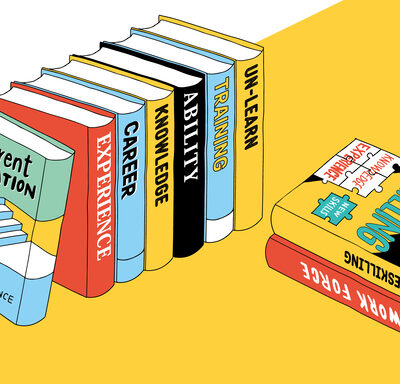こんにちは。古今東西の名作映画を取り上げ、主人公や登場人物をキャリア形成の視点で捉え、人生のヒントを学んでみようというコーナーです。
※ネタバレがありますのでご注意ください。
※映画評やキャリア論を語るものではありません。
山椒大夫
今回は、昭和29年公開の「山椒大夫」を取り上げたいと思います。第15回ヴェネチア国際映画祭で「雨月物語」に続き2年連続で銀獅子賞受賞しています。
監督は溝口健二。原作は森鴎外の小説ですが、元々この物語は、何百年と人々の間で語り継がれてきた説話「さんせう太夫」として有名です。安寿と厨子王は架空の人物とされており、実在していません。
溝口映画は、男性社会で犠牲となってしまう女性をリアルに描くという作風で知られています。もし、溝口監督が今の時代を生きる女性の姿を描いたら、いったいどんな映画が誕生したでしょうか。
さて、映画では強烈なインパクトのあるシーンが数多く出てきます。山椒大夫もただならぬ不適切なオーラを発しています。登場人物はみな壮絶なキャリアを歩んでいます。それでいて、ラストシーンの途方もない美しさはまさに圧巻で、言葉もありません。日本映画を代表する傑作だと思います。
奴隷時代
さっそく、厨子王のキャリアについて見ていきましょう。
まず、映画の中における彼のライフステージを大きく4つに分けてみました。
①悲運な形での父母との別れ
②奴隷として働かされる少年時代
③世直しと復讐
④母との再会
映画では、②から③に移行するさい、ある不思議な出来事が起こります。これをきっかけにして、彼の人生は大きく変わっていきます。いったい彼に何があったのか。どうやって困難を乗り越え、キャリアを築いていったのでしょうか。
まずは状況確認です。②について簡単に振り返ってみましょう。
人買いに騙されて、母と引き離されてしまった兄厨子王と妹安寿。二人は丹後国の山椒大夫に売り飛ばされ、奴隷として強制的に労働させられることになります。当時(時代設定は平安時代末期)、日本には奴隷制度が存在していたことがうかがわれます。
なお、国連IOM「現代奴隷制度の世界の推定」によれば、現代でも、強制労働と強制結婚などで毎日5000万人が奴隷状態にあるとしています。
仮説
本題に入りましょう。厨子王から相談を受けたことにして、キャリアコンサルティングの視点で分析を試みます。まずは、シュロスバーグの4S理論を当てはめて検証してみましょう。
状況(Situation)
長時間労働を強制させられており、過労死ラインを超えている。奴隷なので人権はなく、生命維持として食事のみ与えられている。反抗すれば拷問を受け、逃げたら命はない。こんな人生は予測していなかったし、望んでもいない。
自己(Self)
たとえ出自は貴族でも、今は囚われの身。何もできない。当初は絶望感に苛まれていたが、今はもう慣れた。人生をあきらめたら楽になった。自暴自棄。
支援(Support)
相談できる相手はいない。公共ネットワークから断絶させられている。妹からアドバイスを受けたことがある(ここから逃げて都に出て身を立ててはどうか)。でも、どうやってここから逃げるというのか。見つかったら殺される。
この3つ資源を点検した上で、さて戦略(Strategies)をどう立てるかと考えてみました。しかし、あまりにも深刻な状況で、どう対処すればよいか分からなくなりました。彼を助ける術はあるのでしょうか。
人として彼を見放すわけにはいきません。そこで、自己理解については検証の余地がありそうでしたので、仮説を立ててみました。
厨子王の心内をむりやり現代人に置き換えてみると、彼は「学習性無力感」(心理学者:M.セリグマン)の可能性があります。これは「小象の鎖」の話でご存知の方も多いでしょう。長期にわたり苦痛やストレスにさらされ続けると、そこから逃れようとする力が徐々に失われていき、やがて何をやっても「どうせダメだ」という思考に陥ってしまう現象のことです。
奴隷という特殊な状況ですのでかなり無理はありますが、身近な解釈として、彼はこの現象に陥り、無気力になり、ついに生きる気力さえ失ってしまったと考えられます。
母の声
それでは、映画ではどうなったのか。見ていきます。
ある日、厨子王は上司の命令で、奴隷としての価値がなくなった病女を山中に棄てに行くことになりました。妹の安寿も同行します。二人は一緒に作業をするうちに、幼いころの思い出がよみがえってきたのです。そこで、不思議な出来事が起きます。どこからともなく自分たちの名前を呼ぶ声が聞こえてくるではないですか。「安寿~ 厨子王~」なんと、その声こそ母だったのです。これが引き金となって彼の心は一変し、脱走することを決意。突如として強固な意志をむき出しにして「一緒に逃げよう」と安寿に迫るのでした。
まさかの展開です。先ほどの4S点検および仮説では、厨子王は学習性無力感に陥り、人生をあきらめていたはず。自己効力感はゼロ。安寿のアドバイスさえ受け付けませんでした。それなのに、母の声を聞いたとたん「逃げる」ことを決意し、行動に出たのです。
他方、安寿はどうしたのでしょうか。彼女は「私が時間稼ぎをするから一人で逃げて」といって断ったのです。追手はすぐにやってきます。捕まれば拷問され、兄の居場所を吐かされ、結局殺されます。そんなことは百も承知で、彼女はそれを逆手に取り、わが身の悲運をチャンスとして捉え、兄を逃がそうとしたのです。
これは究極の自己犠牲という名の兄妹愛ではないでしょうか。安寿は自分で決めた道を信じ、最後の最後まで信念を貫こうとしたのです。
辛くも脱走は成功し、厨子王の人生は大きく変わり始めます。ここから前述③世直しと復讐につながっていくのですが、観音像のおかげもあり奇跡が連発し、ついに④ラストでは母との再会を果たすことができました。
厨子王もまた安寿と同じく、命を賭して自分で決めた道を歩み、苦しい現実から抜け出し、人生の危機を乗り越えていったのだと考えられます。その命がけの「逃げる」という決断をさせたのは、まぎれもなく母なのです。もしかしたら、彼にとって本当のカウンセラーは、母だったのかもしれません。
メンター
さらに深掘りすれば、彼の心の中には、父から教わった「慈悲の精神」が宿っていたことがうかがえます。なぜなら、彼は収容施設から逃げ出すさい、今さっき自分が棄てたはずの病女を背中にしょって一緒に逃げたのです。一人でさっさと逃げていれば、それだけ生き延びるチャンスは高まるはずなのに、彼はそうしなかった。彼は慈悲の心を忘れてはいませんでした。父もまた、彼にとって偉大なるメンターだったのかもしれません。
最後になりますが、逃げる誘いを断った安寿はそのあとどうしたかというと、それはこの映画の中でとても重要な場面の一つになりますので、ぜひ映画をご覧いただきたいと思います。
それでは、またいつかどこかでお会いしましょう。