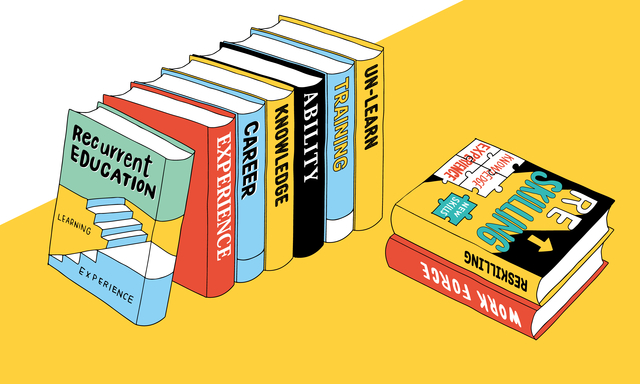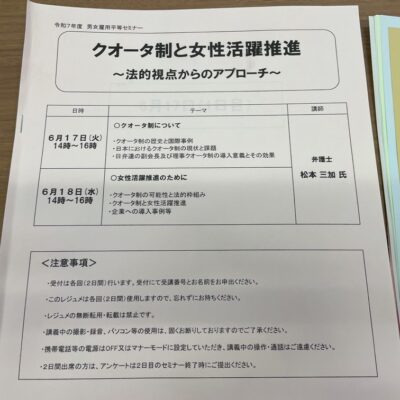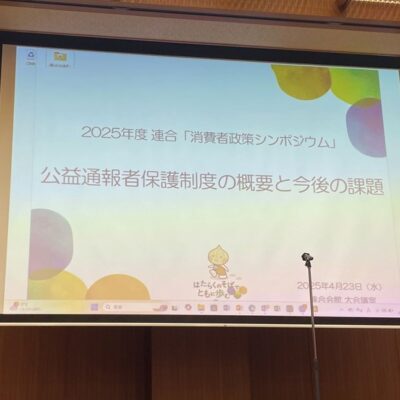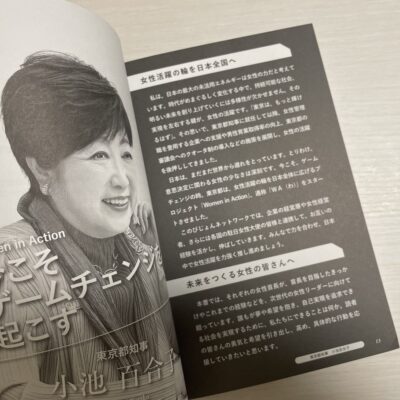Humankind 希望の歴史
ルトガー・ブレグマン『Humankind 希望の歴史』野中香方子訳(文藝春秋2021年)を読みました。
この本は世界46カ国ベストセラー、そして「サピエンス全史」著者ユヴァル・ノア・ハラリ氏推薦とのことで期待値は上がっておりましたが、触れ込み以上に面白く、さわやかな読了でした。
とくに印象に残る点を1つ取り上げてみたいと思います。
新しい現実主義
人に騙されたときの受け止め方として心理学者のマリア・コンニコヴァの著書「The Confidence Game」(Maria Konnikova,2017)を例に挙げ、次のように述べています。
時々は騙されるという事実を受け入れたほうがはるかに良い、と彼女は言う。なぜならそれは、他人を信じるという人生の贅沢を味わうための、小さな代償だからだ。
(中略)
もしあなたが一度も騙されたことがないのなら、基本的に人を信じる気持ちが足りないのではないか、と自問すべきだろう。
引用:ルトガー・ブレグマン『Humankind 希望の歴史』野中香方子訳,エピローグ「人生の指針とするべき10のルール」より
この逆説的な言い回しには思わず唸ってしまいました(きっと翻訳もすばらしいのでしょう)。
そもそも「善」というものは主観的です。自分は善だと考えていても、他人からすればそれは悪かもしれません。人は追い詰められると凶暴になりがちですから、善と善がぶつかって信頼関係が崩壊するケースはよくあることです。
人々は「何が善なのか」について分かり合えていません。だからこそ、人をもっと信じようじゃないかと著者は力説します。
子どもの頃、ザ・ブルーハーツの「TRAIN-TRAIN」が好きでよく歌っていましたが、歌の中で『いいやつばかりじゃないけど、悪いやつばかりでもない』という一節が出てきます。
この歌のように「いい」と「悪い」のバランス感覚の妙も、新しい現実主義では大切になってくると著者は示唆します。
単にお人好しじゃダメ。とはいえ恐れていては何も始まらないよね。悲観せず、無知から抜け出そう。勇気を持って人を信じよう。そこからすべてが始まるんだよ、といって応援してくれている気分になりました。
能登のおばあちゃん
ニッポン放送「おしゃべりラボ~しあわせ Social Design」(3月16日放送)のゲストに、映画監督の石井かほりさんがご出演されました。
その番組の中で、監督は石川県能登の杜氏をテーマにした映画「一献の系譜」のロケ中の出来事で、柿を枝ごともぎ取るおばあちゃんの話をされておりました。
出典:映画『一献の系譜』公式サイト
http://ikkon-movie.com/
そのおばちゃんにとって石井監督はよそ者(不審者)です。そのよそ者に対し、脱水症状になるんじゃないかと心配して柿を差し出すおばあちゃん。
なんと心優しいのでしょうか。まさしく「能登はやさしや土までも」を地で行くようなエピソードでした。
そのとき、この本の下巻「Part5 もう一方の頬を」の冒頭「ブロンクスで働くフリオ・ディアという若者が強盗に遭う話」を思い出したのです。
「おーい、ちょっと待って」と、彼は強盗を追いかけた。「今晩、この後も盗みをするつもりなら、わたしのコートも取り上げて、暖かくしていきなさい」
引用:ルトガー・ブレグマン『Humankind 希望の歴史』野中香方子訳,下巻「Part5 もう一方の頬を」より
若者が強盗にコートを差し出し、そのあと夕食までごちそうするというエピソードです。
この若者と能登のおばあちゃんが頭の中でつながったのです。この2人は根っこの部分が同じだと思いました。
敵に最善を尽くすのは容易ではありませんね。でもこの本のおかげ様で、テロリストとお茶を飲むことが出来そうな気になってきました。