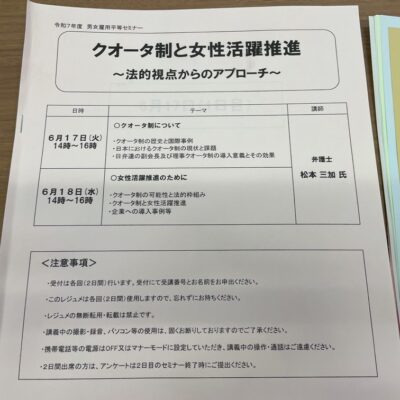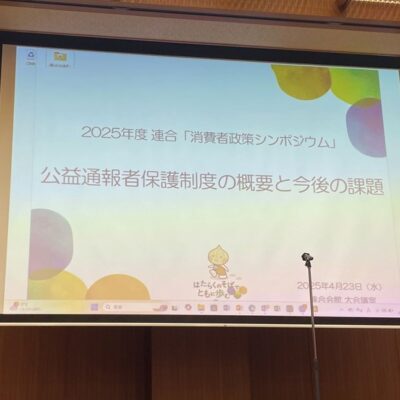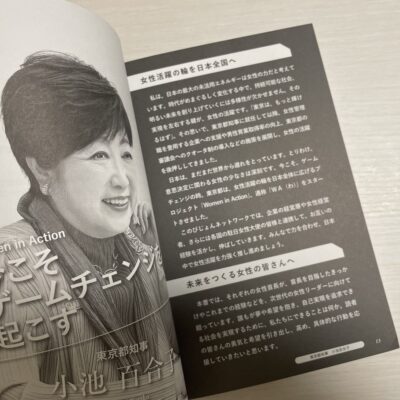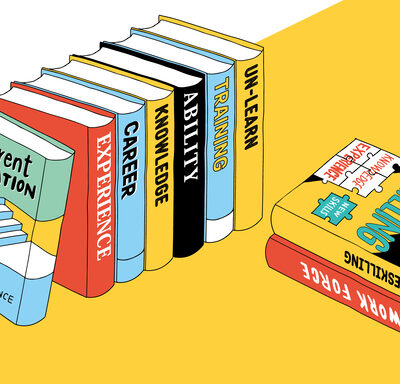こんにちは。古今東西の名作映画を取り上げ、主人公や登場人物をキャリア形成の視点で捉え、人生のヒントを学んでみようというコーナーです。
※ネタバレがありますのでご注意ください。
セント・オブ・ウーマン/夢の香り
今回は1992年アメリカ映画「セント・オブ・ウーマン/夢の香り」を取り上げたいと思います。監督はマーティン・ブレスト、脚本はボー・ゴールドマン、出演はアル・パチーノ、クリス・オドネル、ガブリエル・アンウォーほか。
本作品はアル・パチーノがアカデミー主演男優賞、ゴールデングローブ賞では最優秀作品賞(ドラマ部門)、主演男優賞、脚本賞を受賞しました。
「言えません」という選択
それでは、名門校に通うチャーリー・シムズのキャリアについて見ていきましょう。
この映画の核となる部分ですが、チャーリーは同級生らが校長の愛車にいたずらをするところを目撃してしまったがために、思いもよらず人生の岐路に立たされるという一連の流れを検証してみます。
チャーリーは校長から二択を突きつけられます。犯人は誰だと。正直に答えればハーバードへの切符が手に入る。さもなくば退学だと。
さすがは校長。御曹司であるウィルス君の身柄は釈放し、コネもカネもない田舎者チャーリーを標的にします。ここぞとばかり職権を活用し、夢をチラつかせては揺さぶりをかけるという、なんという粋な計らいでしょうか。
チャーリーは2度、正直に告白するチャンスがありました。校長室と全校集会です。しかし、そのどちらも「言えません」と答え、最後まで犯人の名を明かしませんでした。
こと全校集会において校長は couldn’t say か wouldn’t say かと細かく詰め寄りますが、チャーリーは I just couldn’t と答えるのでした。
チャーリーは、犯人が誰なのか知っていたはずです。現場に居合わせたウィルス君が「あいつらだ」と言って口笛まで吹いていたのですし、その隣にいたチャーリーも「あいつら」を十分に認識していた表情と態度をとっています。
それでも「言えません」を突き通したのです。
はたして、チャーリーは嘘つきなのでしょうか、それとも仲間をかばったのでしょうか?
校長室でのやり取りでは、ウィルス君に引っ張られたのか「確証がない」などと発言していることから、少しは仲間をかばう気持ちもあったのでしょう。ここでバラせば裏切者として烙印を押されます。そしたら、いじめられるかもしれませんし、学校ではもう居場所がなくなるかもしれません。
正直者は不正義か?
反面、チャーリーは事実を語ることで「正直者」として校長から高く評価(利用)されるはずでした。その上、ハーバードへの切符も手に入ったはずです。
それでもなぜ、彼は拒否したのか。なぜ、エリートの道を潰してまで口を割らなかったのでしょうか。
その理由は、フランク・スレード中佐のセリフに凝縮されています。中佐は全校集会で「彼は自分の得のために友達を売る人間ではない」と彼を擁護した上で、こう熱弁しました。
私も何度か人生の岐路に立った。どっちの道が正しいかは判断できた。だが、その道を行かなかった。なぜだかわかるか? それは困難な道だったからだ。
チャーリーも岐路に直面した。そして彼は正しい道を選んだ。真の人間を形成する信念の道だ。
フランク・スレード中佐
全校生徒の前で尋問を受けたチャーリーは、自分の気持ちをうまく言語化することができず窮地に立たされます。そこへ中佐が登場。饒舌な語り口で彼を救ったのです。
中佐は人間の本性を見抜くことに長けた優れた能力を持っているようです。そしてまた、チャーリーとはニューヨークでのはちゃめちゃ旅行で心を通わせた間柄です。そんな中佐が、彼の沈黙を魂レベルで理解し、昇華させ、代弁したのです。一人で闘い、追い詰められ、崩壊寸前だったチャーリーにとって、中佐の存在は偉大すぎます。
高潔と勇気
一方で、校長はとことん悪者扱いをされています。そもそも校長は被害者であるということを忘れてはなりません。また、校長の主張する「チャーリーは事実を隠ぺいし、虚偽の証言をした」という見解も筋が通っています。
弱みにつけ込んだ取引を迫るその手口はいけ好かないですが、校長の言い分も大いに汲みすべきでしょう(あくまで映画なので余計な忖度はしないでおきます)。
この映画の主訴は「人は人としてどう生きるべきか」を投げかけているのではないでしょうか。その答えの一つとして「高潔と勇気」が描かれているのだと思います。
その高潔と勇気がもたらすキャリア観は、学歴や出世よりも「自分に正直に生きる」ことの大切さを気づかせてくれます。たとえそれが茨の道だと分かっていても。
チャーリーのその態度は一見して頑固で不誠実です。これでは信頼関係を損ねたり、誤解を招くおそれがあります。でもそれは単なる気まぐれや意地悪などではなく、彼の信念に基づく態度なのです。
「言えません」と答えることで自分自身でいようとしたチャーリー。彼は自分らしく生きるために勇気をふりしぼって闘ったのです。逃げることなく最後まで。こうしたプロセスの一つひとつの積み重ねが、彼のキャリアを形成していくのだと思います。
I got no life!
ほかにも、キャリアを形成する上で重要な考え方が示唆されています。その一つは、何と言っても、中佐とドナが華麗に躍るタンゴ。これは映画史に残る名場面ですね。
間違えることが怖いとためらうドナに対し、
タンゴは人生と違い間違わない 簡単なところがすばらしい 足が絡まっても踊り続ければいい
フランク・スレード中佐
といって口説き、ドナを誘います。
「失敗や迷いがあっても(足が絡まっても)立ち止まらずに挑戦し続ける(踊り続ける)ことが重要だ」という解釈ができます。
また、フェラーリを乗り回すシーンもしかり。「目が見えないなんて関係ねえ!」といった勢いで街中を走り回る中佐。かっこいいですね。
このシーンは、「自分で限界を作ったり可能性を狭めたりするな。リスクを恐れず、やりたいことをやれ」といったメッセージが込められているのではないでしょうか。
その点、中佐は I got no life!と絶望し、死を考えていました。自分の人生を受け入れることができず、もがき苦しんでいたのです。それでもなんとかして光(希望)を見たかったのではないでしょうか。そんな中佐の生き様から、チャーリーは光を見ることの大切さを学んだことでしょう。
チャップリンへのオマージュ
ところで、本作品はチャップリン愛にあふれていると思いませんか。まず「チャーリー」という名前。そして盲目という設定。ほかにも金持ちと貧困のコントラスト、全校集会での中佐の独演、そして幕引きはラ・ヴィオレテラ。チャップリンファンにはたまりませんね。
それでは、またいつかどこかでお会いしましょう。